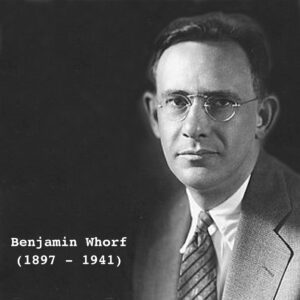写真はMAPIにて、アフリカ代表のChizuruoke Sufficient Aruaと。彼女の明るい笑顔はアフリカの宝だと思う。巨大な会場でもひときわ輝いていた。
さて、
「事実や根拠に基づく話が出来ない人間とは、話すだけ時間の浪費である」
アメリカ建国の父と言われるイーサン・アレン(1738 – 1789)のことばである。
私は、論理的思考の中で育った。
子どものころから、宗教的な熱心さで「フェアな議論」こそが人間のあるべき姿だと信じていた。
やがて社会科学の道に進み、世界中の優秀な研究者に囲まれる中で、私の信念はより強化された。
正しき論理性こそ、ソクラテス以来の人類の叡智であり、それを守ることが、世界をより良くする道だと信じていた。
論理は重要だ。
事実と根拠のない話では、世界において信頼を得ることはできない。
だが、そこには見落とされがちな“前提”がある。
「全員がそのルールを守っている」時にのみ、論理は有効であるということだ。
修辞学者・香西秀信教授(1958–2013)はこう言った。
「論理的思考力や議論の能力など、所詮は弱者の当てにならない護身術である。強者にとって議論のルールなど、弱者の甘え以外の何ものでもない。」
「詭弁だのルール違反だのと非難するのは、『後生だからそんな手は使わんでくだされ』と、弱者が悲鳴を上げているのだ。そして、その悲鳴を、さも“勝利宣言”のように告げるのも、また弱者の特徴である。」
痛烈だが、本質を突いている。
現実世界では、人間は平等ではない。
守られたアカデミアのような世界でもそうだが、実社会では「対等な人間関係」で「フェアな議論」ができる場面など、ほぼ存在しない。
たとえアメリカのように「フェアなディベート」が社会の伝統になっている国ですら、権力者が本気で対等な議論をするなど、ほぼない。
権力者にとって、「あなたとフェアに話し合おう」などという発想は1ミリもないよ。
その前提での「フェアに見える議論」でしかない。
すなわち、彼らを論破しようとすること自体が“世間知らず”とも言える。
たとえ議論に“勝った”としても、現実において失うものの方がはるかに大きい。
これは、日常の人間関係でも同じだ。
たとえば夫婦関係でも、力関係に差があれば、議論は成立しない。
私自身、少年時代にそれを思い知った。
私は、父親と話が通じなかった。
エディプスコンプレックスだったのかもしれない。
私は父親に勝ちたかった。父親に認められたかった。父親をギャプンと言わせたかった。
「なぜ、まともな話し合いができないのか?」
私は10歳の頃から悩み続け、その問いの答えを見つけるまでに30年以上かかった。
結果として、私は父を論破したわけではない。
むしろ、議論そのものを完全に手放した。
ギャフンと言わせる30年来の欲望を放棄した。
そのとき、初めて父が変わった。
私も変わった。
「愛してるよ」と面と向かって素直に言えるような関係になった。
私は、「正しき議論」への執着こそが、対話を妨げていたことに気づいた。
これは、英語教育にも当てはまる。
多くの人が、語学力というものに過度な執着をしている。
「正しい文法」「TOEICの高得点」「論理的に話す力」
これらは確かに一見役に立ちそうだ。
だが香西教授の言葉を借りれば、それらはすべて、
「弱者の当てにならない護身術」なのだ。
たとえば、護身術のクラスでこんなことを習ったとしよう。
「まず相手のナイフを取り上げ、それから手首をひねって制圧します」
それを、実戦で本当にできるだろうか?
現実は、教科書通りにはいかない。
語学も同じだ。
日本の英語教育は、当てにならない護身術のようなものを「これが武道だ」と教えている。
あなたがいくつもの英会話スクールに通い、何年も努力しても、
いざという時に通じない理由は、そこにある。
英語は、試験科目ではない。
武器であり、自己表現であり、あなたの人生そのものだ。
英語の響きを受け取れる身体、
心を通わせられる自由な英語、
相手の奥深くまで届く“声”
を得たいなら、視点を変えなければならない。
語学レベルが初級や上級なんて何の関係もない。
あなたは変われる。
手がかりを求めているあなたへ

升砲館 金剛會 ショーンツジイ
プロイングリッシュスピーカー育成ディレクター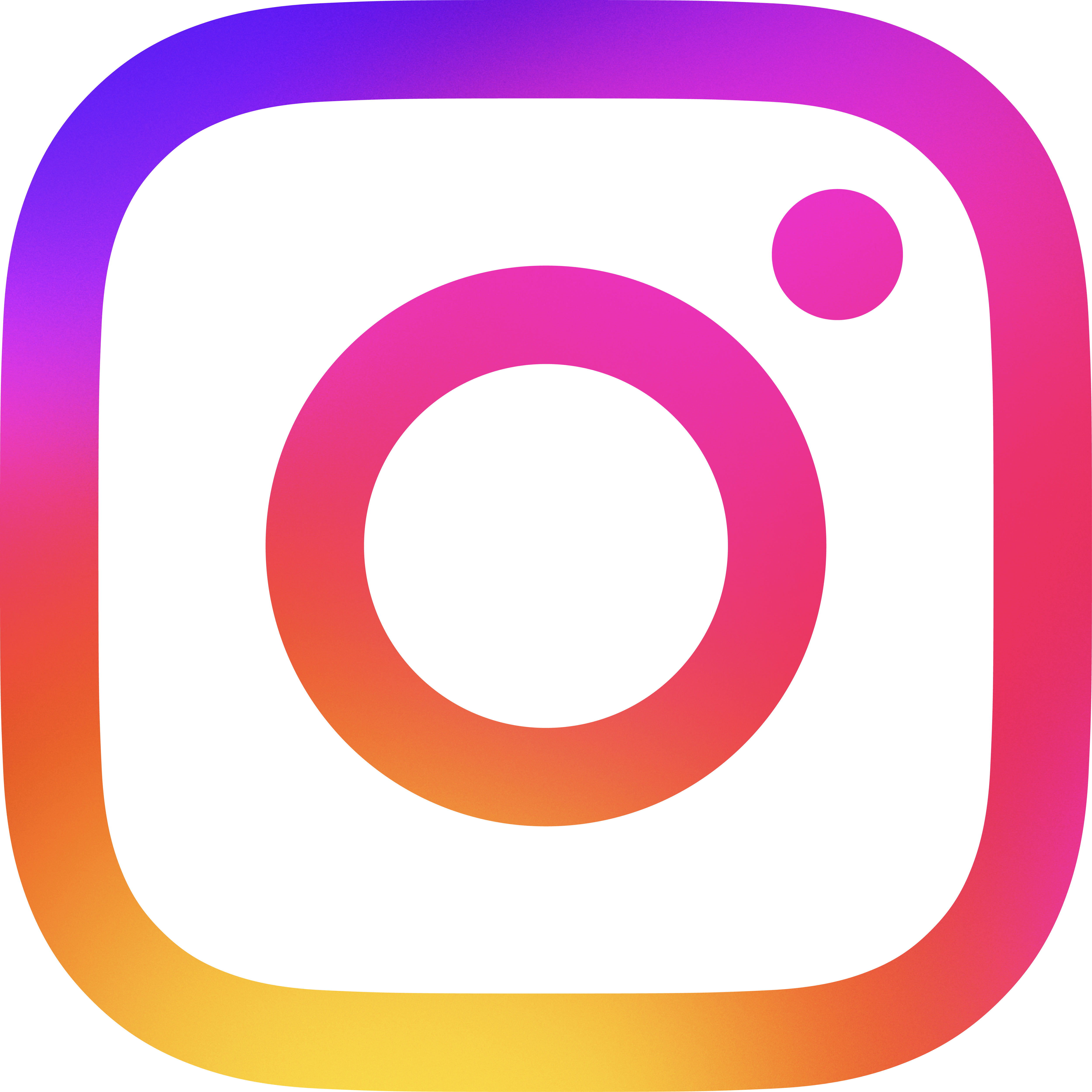

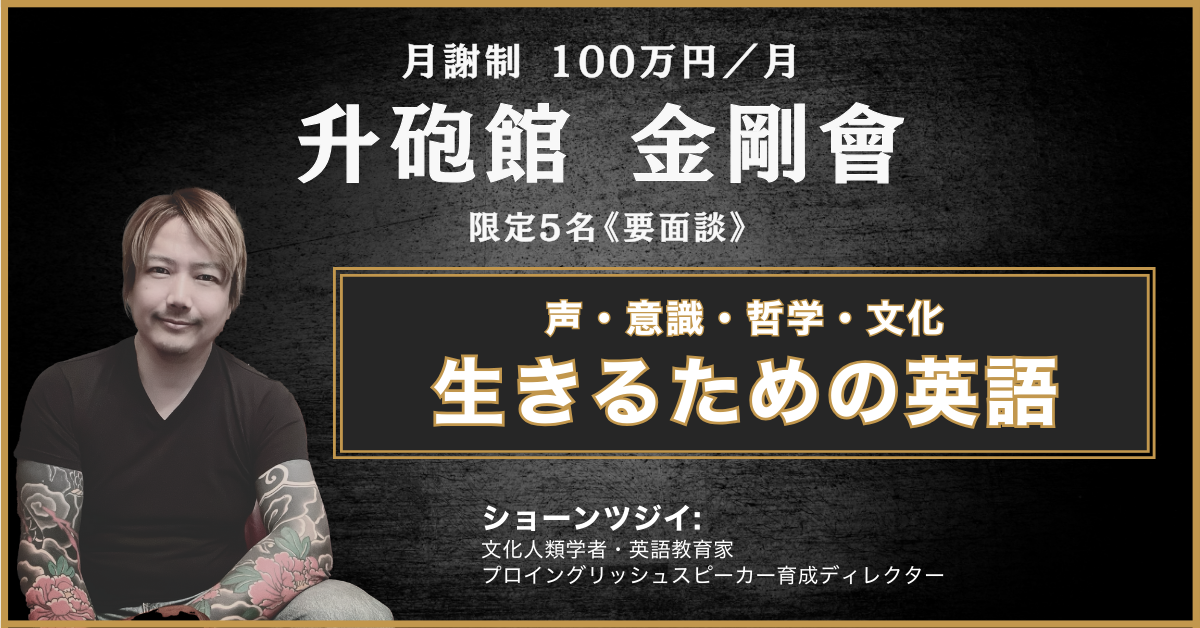
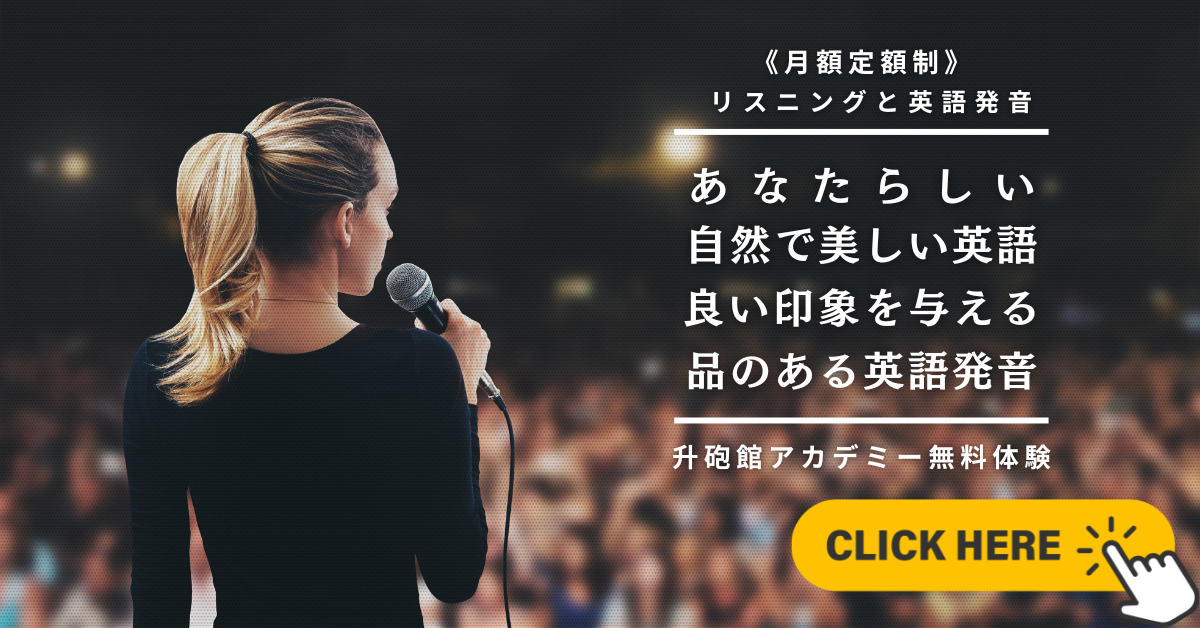
あなたの英語は変わるかもしれない