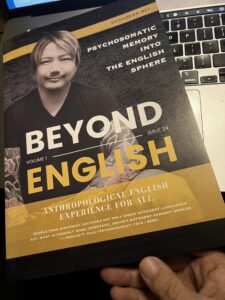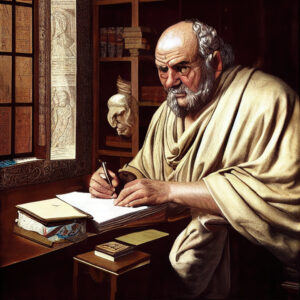写真は京都の曼殊院。
さて、夏が来た。この季節になると、決まって耳にする言説がある。
「虫の音が聞こえるのは、日本人だけ。
西洋人には虫の音が聞こえない。」
いや、それ本当?と思う。
この “虫の音問題” に関しては、文化人類学者のエドワード・T・ホールと、脳科学者の角田忠信博士が、それぞれ異なる角度から興味深いアプローチをしている。
エドワード・T・ホール、「日本人には虫の音が音楽や情緒として知覚されるが、欧米人にとってそれはノイズ、あるいは背景音でしかない」と述べた。これは文化による知覚の差異に注目したものだ。
一方、角田博士は、虫の声を処理する脳の部位に注目する。
日本人は虫の音を左脳(言語脳)で処理するが、西洋人は右脳(音楽脳)で処理するという。
つまり、日本人にとって虫の音は“意味ある音”として聞こえ、西洋人にとっては“非言語音”=BGMに近い存在として聞こえる、と。
自分の研究分野でもあるので、私も両者の研究は興味を持って読んだ。
だが、それにしても、
「西洋人には虫の音が聞こえない」
というのは、いささか飛躍が過ぎる。
そもそもこの説、日本でしか聞いたことがない。
一体だれが最初に言い出したのだろう?
サピア=ウォーフ仮説的に言えば、これは「世界の見え方は言語によって変わる」ということ。
つまり、「虫の音」というカテゴリーがある日本語と、そうした分類が曖昧な英語圏では、同じ音を違う概念として捉えているにすぎない。
英語圏では、鳥の声も虫の音も含めて「noise(ノイズ)」と呼ばれる。
日本語で「雑音」と訳されるこの単語は、ネガティブな印象がある。
だが、英語における“noise”はもう少しニュートラルで、「自然音」や「動物の出す音」を含む。
この翻訳のズレが、「日本人にしか虫の音が聞こえない」という都市伝説を生んだのかもしれない。
とはいえ、
「日本人は情緒豊かだから虫の音が聞こえるんだ」
「日本語には“虫の声”という美しい概念がある」
そういう誇りやロマンを否定する気はない。
だが、事実と感性は、区別されるべきだ。
例えるなら、関東では「バカ」と言い、関西では「アホ」と言う。
呼び方が違うからといって、東京にアホがいないわけじゃない。
同じように、虫の音を「voice of insects」と呼ぶか、「background noise」と呼ぶかの違いであって、聞こえていないわけではないよ。
ちなみに、1980年代のUKポップデュオ、Wham!の有名曲”Club Tropicana”を聞いてみてほしい。
曲の冒頭、約30秒間に流れる音。あれは、何の音?
そう、虫の音である。
わざわざそれをサンプリングしてまで曲の“演出”に使っているのは、なぜか?
もし「イギリス人に虫の音が聞こえていない」なら、そんなこと、するはずがないのでは!?

升砲館 金剛會 ショーンツジイ
プロイングリッシュスピーカー育成ディレクター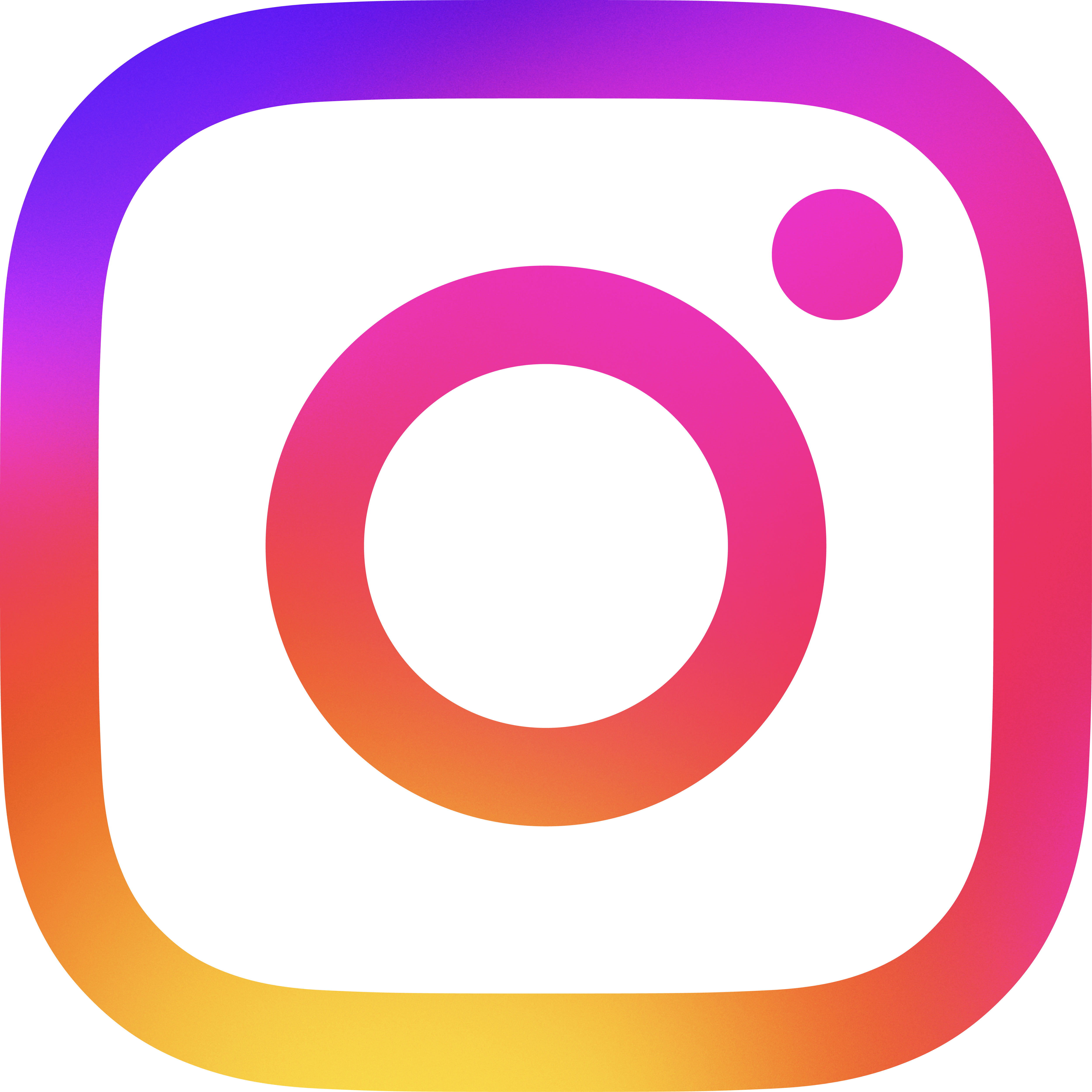

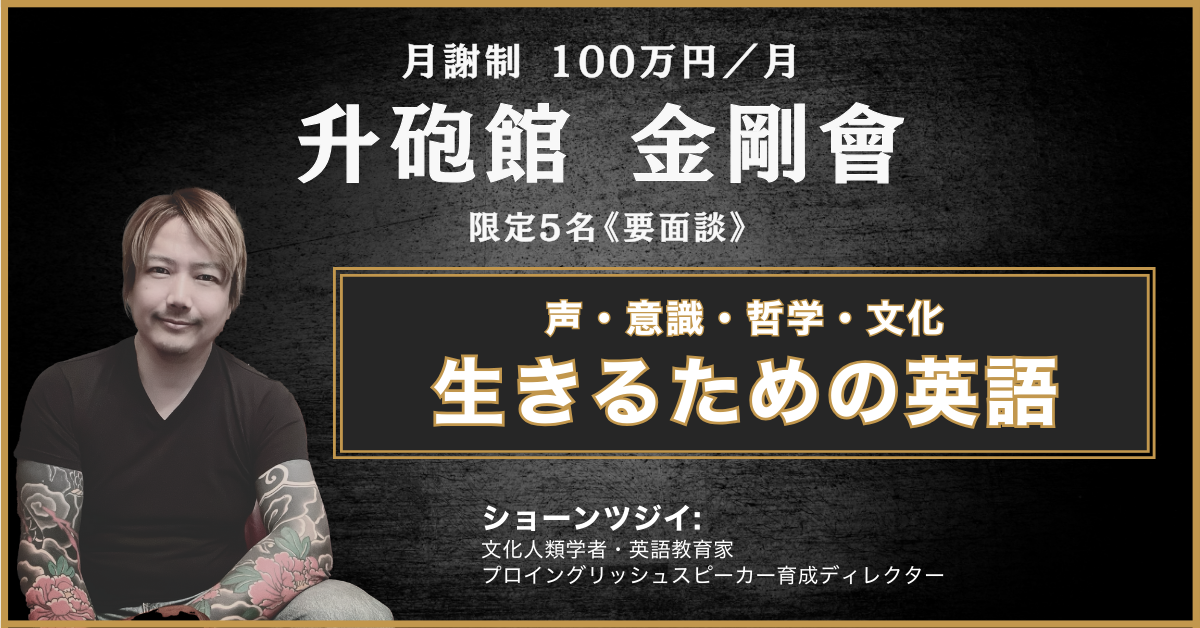
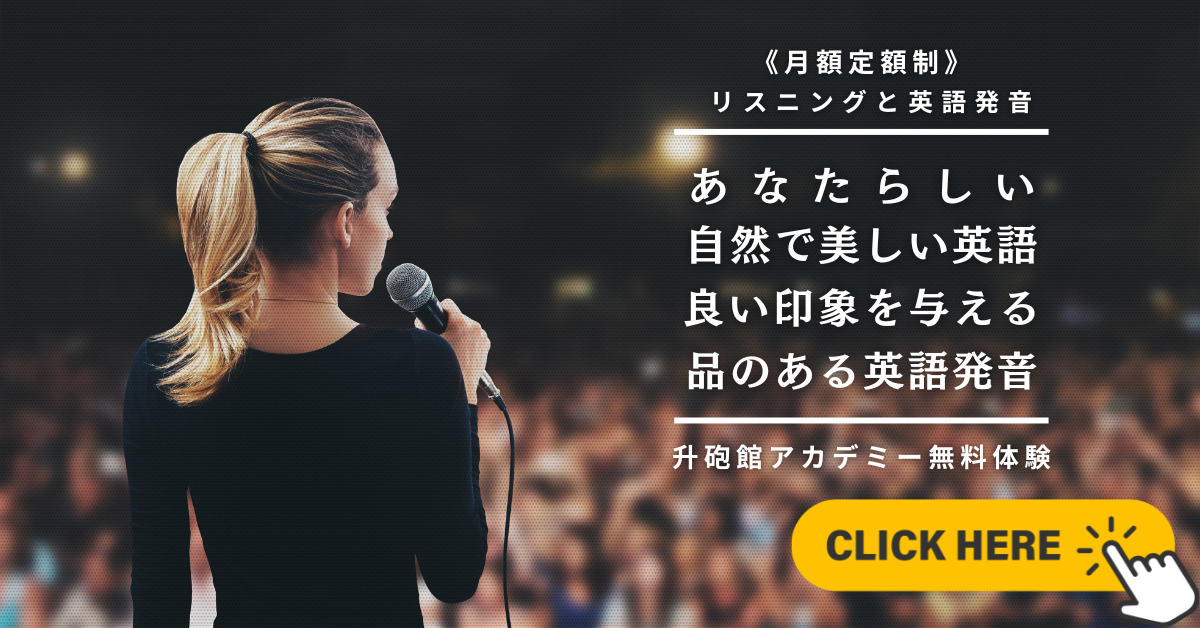
あなたの英語は変わるかもしれない