写真は、母校立命館高校の豊田先輩と于先輩と撮ったもの。豊田先輩は心優しき憂国の士。于先輩は、四条大橋西詰にある京都の名門中華料理店、東華菜館のオーナー。卒業してからいつまで経っても、二人とも大好きな先輩だ。
さて、私はかつて、京都大学大学院で「プレゼンテーション技法」の講義を2年に渡って担当したことがある。海外からの留学生たちが履修するクラスだったので全て英語による講義だったが、その講義には数名、日本人の学生も混じっていた。彼らは懸命に食らいつき、慣れない英語でのプレゼンに必死に取り組んでいた。
ホントに皆ががんばっていた。
思い出すと、胸が熱くなる。
だが、それとは対照的な、ある「悲劇」のエピソードがある。
数年前、親しい友人から聞いた話だ。
ある日本人の高校生の女子が、オーストラリアかニュージーランドの高校に留学に行った。
その学校には、彼女のほかにも中国、韓国からの留学生が在籍していた。
ある日、留学生代表としてその3人が、地元の市長主催のパーティに招かれた。
こういう公的な場でスピーチを求められることは、英語圏ではごく当たり前のことである。
だが、彼らにその事前情報はなかった。
即興でのスピーチを求められたその場、
最初に立ったのは中国人の留学生。自国の歴史や文化を、堂々と英語で紹介した。
次に登壇した韓国人の留学生も、韓国の魅力を流暢な英語で語った。
最後に紹介されたのが、日本人の彼女だった。
だが、彼女は、自分の名前を名乗っただけで、立ち尽くしたという。
目の前が真っ白になり、言葉が出なかったのだ。
その彼女は、日本ではいわゆる「成績優秀な生徒」として知られていた。
進学校に通い、内申点も高く、模試の偏差値も上位。
つまり、日本の教育システムの中では、明らかに“エリート”の枠にいた。
しかし、英語圏の現実は非情である。
高校生であっても、自分の意見を持ち、人前でしっかり話せることが当然とされる。
とくに留学生は、その国の“代表”として見られるのだ。
中国人も韓国人も、まさにその役目を果たした。
だが、日本人の彼女は何も語れなかった。
何が足りなかったのか?
語彙か? 文法か? リスニングか? 発音か?
違う。
本質は、「声」であり、「勇気」であり、「訓練」だった。
知識偏重社会の落とし穴がある。
日本では、「知識」さえあれば、かなりの程度まで評価される。
人前で話せなくても、読み書きができれば“優等生”として扱われる。
だが、世界は違う。
世界は、「語れる者」しか、生き残れない。
「伝えられる者」しか、リーダーにはなれない。
ましてや、グローバル社会で求められるのは、“表現力”と“自己の確立”だ。
この2つが欠けた「日本型エリート」は、いとも簡単に砕け散る。
木っ端微塵なのだ。
この話は、誰かを責めるためのものではない。
むしろ、「今、この瞬間から始められることがある」という希望の物語だ。
頭でっかちの知識主義を脱し、
本当の意味で“語れる自分”を、ゼロから育て直す。
それは、TOEICでも文法でもない。
声を取り戻すこと
自信を取り戻すこと
魂のこもったことばを、他者に届けること
その先にしか、真の国際人への道はないよ。
この世は公平ではない。
儒教思想の東アジア地域は特にその影響が強いが、性善説も幻想。
この世には、悪い人間がうようよいる。
戦争が終わり非武装となった途端、隣国に攻め入れらて、領土や生命財産を奪われたり、
被害者数を盛りまくって、なんと当時の人口以上の民間人が虐殺されたと主張して賠償を求めてきたり。
卑怯な方法にやられてばかりの、お人よしの日本。。。
日本人よ、誇りを取り戻そう!
日本の学生の子たち、留学に行って、胸を張って言いたいことを言ってきてくれ!
ハーバードのサマースクールでスピーチコンテストに挑戦してくれたまえ!
現地の人や現地メディアを「こんな日本人初めて見た!」と驚かせてきてくれ!
日本では「目立つようなことはせず、おとなしくしている」のが真面目だが、アメリカの真面目は「傍観せず、皆のために立ち上がる、勇気ある良き市民のこと」である。
アメリカの高校の校則には、そういうことが書いてあるのだが、国が違えば「真面目」の定義も全く違ってくる。
ことばを乗り越えて、皆が対等にお互いを尊重し合える社会が来てくれますように。
まず、日本人は「声」と「自信」を取り戻そう。

升砲館 金剛會 ショーンツジイ
プロイングリッシュスピーカー育成ディレクター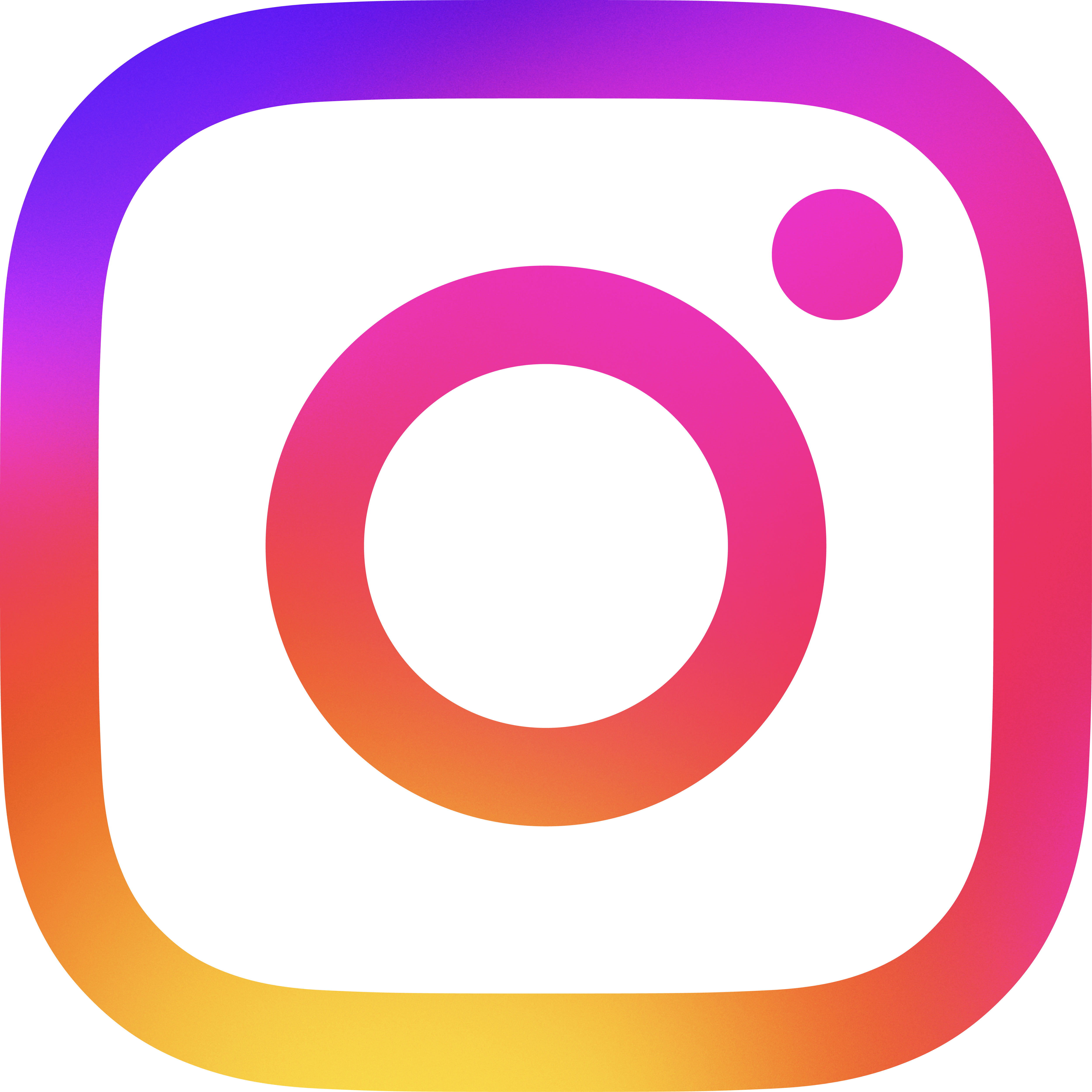

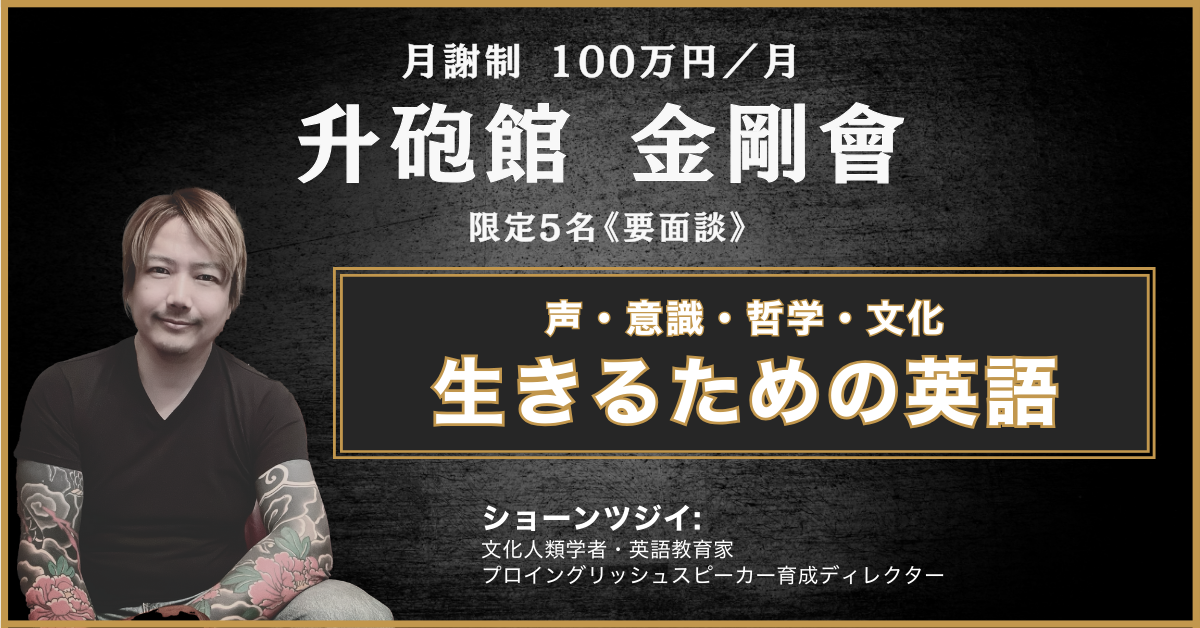
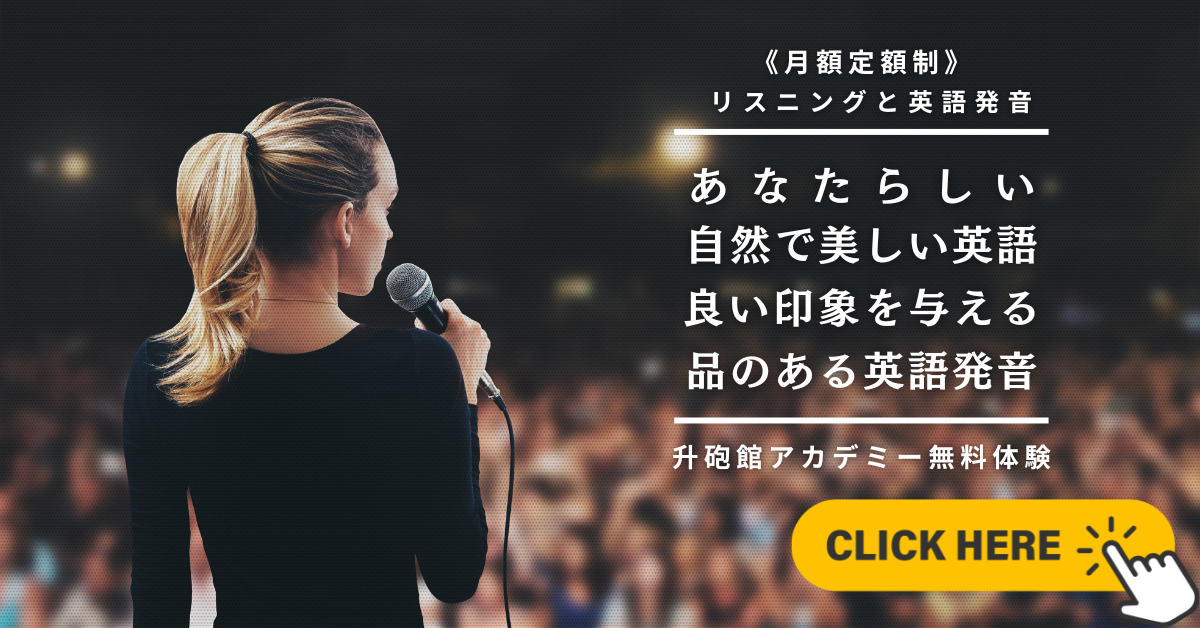
あなたの英語は変わるかもしれない












