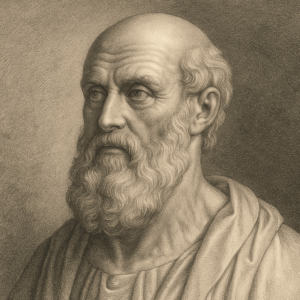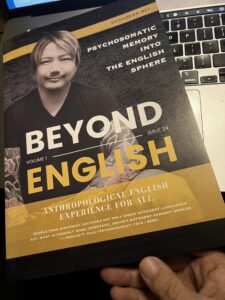写真は義息子と横浜で。横浜のスカーフ大使として多くの人に愛された小柳デニス貴駿。いやぁ、佐久間象山(江戸時代の思想家)みたいな男前でうらやましい。
さて、今日の本題はこうだ。
「英語が話せるようになったから変われたのではない。
変われたから、英語が話せるようになったのだ。」
じゃあ、どうすれば「変われる」のか?
どうすれば、自分らしい自然な英語を、自由に話せるようになるのか?
鍵になるのは、「分類わけ」の罠に気づくことだ。
男前と非男前。
外向的と内向的。
上手いと下手、美しいと醜い、陽キャと陰キャ、、、
私たちは、言葉というラベルで世界を切り分けながら生きている。
それはまるで、世界を冷蔵庫に小分け保存するような感覚だ。
便利だ。整理整頓できる。理解しやすい。
だがその瞬間、
「いのち」は“データ”に変わり、
「ひかり」は“定義”に閉じ込められてしまう。
以下の寓話を読んでほしい。
///////////////////////////
『風を縛る名前』
ある村に、空を舞う風があった。
誰よりも自由で、誰にも捕まらなかった。
ある日、学者がそれを見て言った。
「これは“南東の風”と名づけよう。分類できれば、理解できる。」
それから人々はその風を「南東の風」と呼び、季節の一部として扱った。
誰ももう、風のささやきに耳を澄まさなくなった。
風は次第に、吹く理由を忘れていった。
踊りも、歌も、失われた。
だがある夜、小さな子が囁いた。
「あなた、なまえなんていらないよね。」
そのとき、風ははじめて泣いた。
そして、笑った。
名もなきものとして、再び空を駆けた。
///////////////////////////
人見知り、声が小さい、内向的、継続力がない、発音が悪い、、、
気づかぬうちに私たちは、
他人から、そして自分自身から、無数のラベルを貼られている。
だがそのラベルの下にある「本当のあなた」は、
いまだ名付けられたことのない風なのだ。
クリシュナムルティの後継者的立場(と私が考えている)のドイツ出身のエックハルト・トールは言った。
「名前をつけた瞬間に、そのものの“生きた本質”は失われる」
フランスの哲学者ミシェル・フーコーもまた、こう主張した。
「言葉によって、現実はつくられている」
小説『1984年』でジョージ・オーウェルが描いたのは、
言語を統制することで、人間の思考そのものをコントロールする社会だった。
つまり、言語が操作されれば、思考もコントロールされてしまうということだ。
科学の目的は、世界を分類し、体系化することだった。
それは美しくもあるが、同時に危うさもはぐくむ。
分類の中で、本来あったはずの神秘性・野生性・生きた力が削ぎ落とされる。
人は「自分とはこういう存在だ」と定義した瞬間、
“風”であることをやめ、“カテゴリー”になってしまう。
哲学者ホセ・オルテガ・イ・ガセットは言った。
「細分化されたサイエンス、専門家が、大衆を愚民たらしめている」
知識が増えても、風にはなれない。
語彙が増えても、魂は話せない。
英語は、“変わったあなた”だけが語れるものだ。
ラベルを脱ぎ捨てよ。
そして、名前のない風となって、もう一度、自由に吹き始めよう。
風の時代だしね。
PS 私が一番嫌なのが、英語教師や英会話講師たち。自らを「先生」とカテゴライズしていて偉そう。「生徒」というカテゴリーで学習者を見ている。あなたは「生徒」というカテゴリーから抜け出れなくなり、英語がうまくなる機会を奪われる。

升砲館 金剛會 ショーンツジイ
プロイングリッシュスピーカー育成ディレクター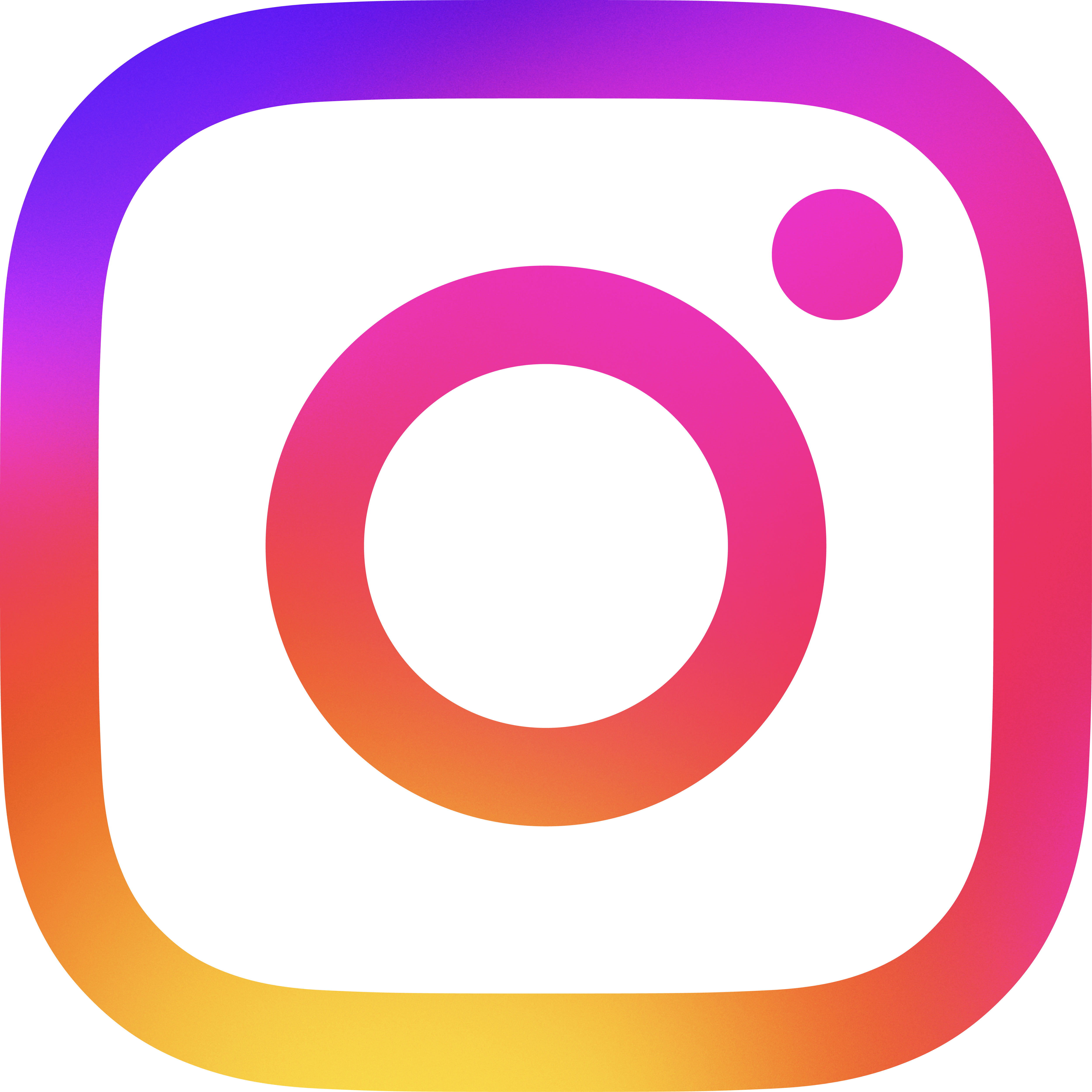

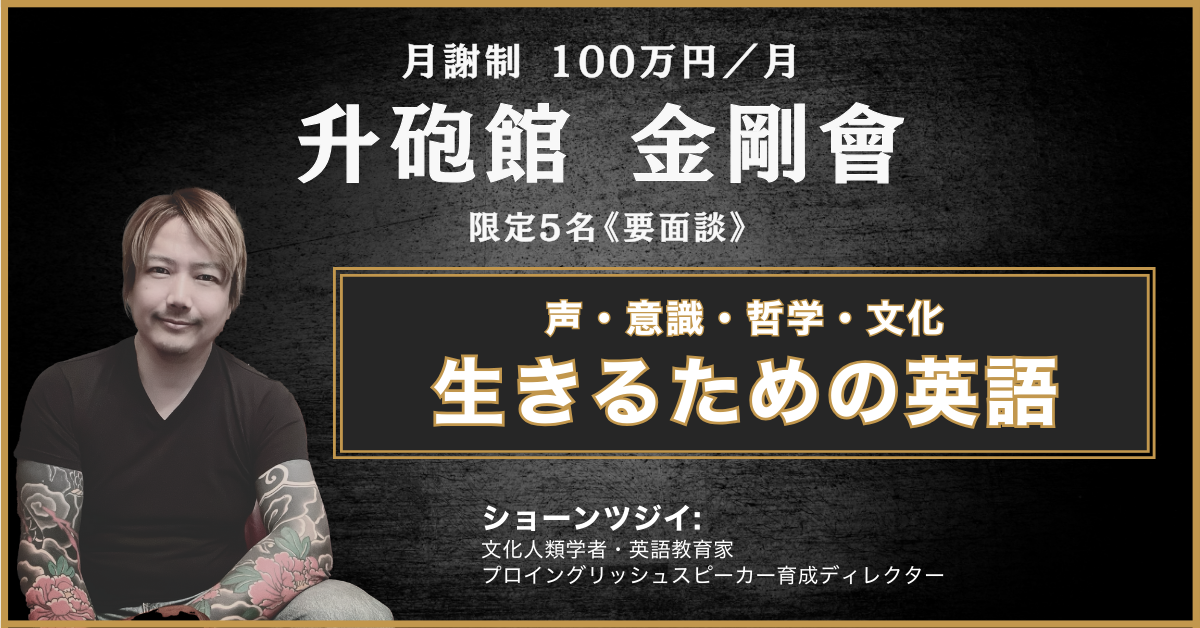
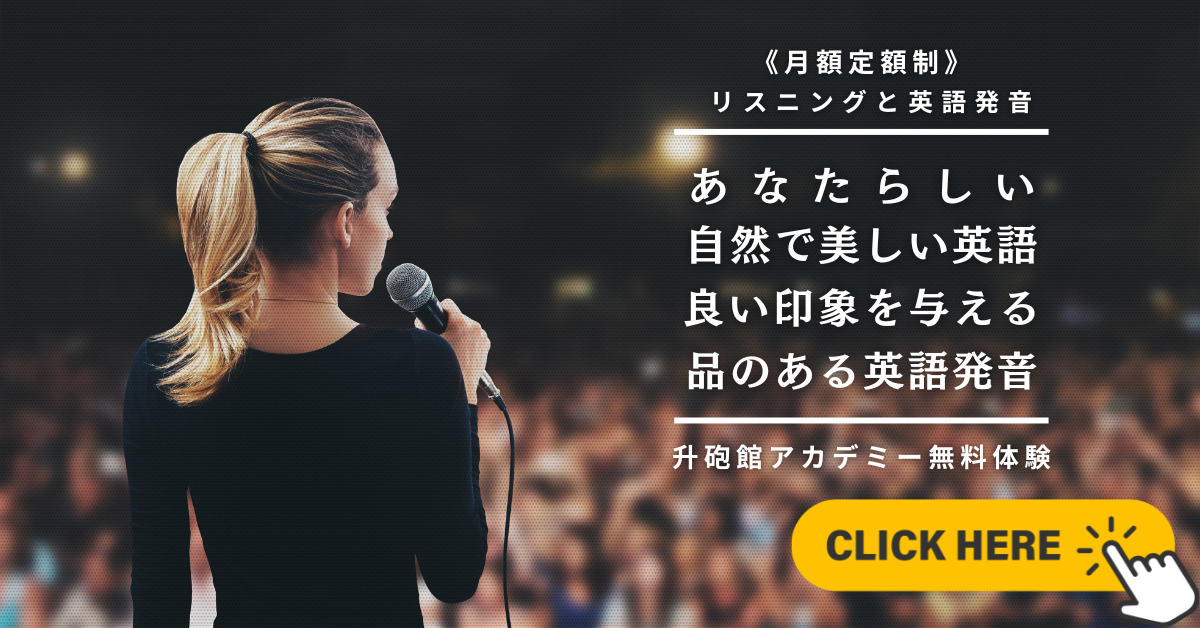
あなたの英語は変わるかもしれない